トレーニング理論でよく耳にする「80/20」。
こちらについて GTN (Global Triathlon Network) が、視聴者からの質問に答える形で解説をしております(英語です)。
80/20 Training: Does The Warm-Up Count? | GTN Coach’s Corner
How Does 80/20 Training Really Work? | GTN Coach’s Corner
これら 2つをこの 1記事にまとめてみました。
結論を先に書いておきます。
80/20 の低強度/高強度の定義は、自分の感覚を基準にする。
80/20 の割合は厳密でなくても良い。
80/20 はハイレベルの選手向けである。
一般のアスリートは、回復力をベースにして高強度の割合を考える。
80/20ルールとは
80/20の理論は、遠泳、ロードバイク、ランニング、トライアスロン等の持久系競技において、練習の80%を低強度で、20%を高強度で行うことで、怪我のリスクを抑えつつ、心肺機能や筋持久力や VO2Max 等を伸ばせる、つまり競技能力を向上できる、というものです。
この概念を広めたのは Matt Fitzgerald 氏で、著書の 80/20 Running や 80/20 Triathlon は代表作となってます。
Fitzgerald 氏は、この高強度・低強度については、自身の感覚をベースにすることを勧めています。
RPE: Received Rate of Perceived Exertion (主観的運動強度・自覚的運動強度) を基準にしたりする、ということです。
最大心拍数とか FTP を基準にしている訳ではないんですね。
Polarized Training とは似て非なるもの
似たようなトレーニングに Polarized Training というものがあります。
これはノルウェーの Stephen Seiler 博士が提唱し、ノルウェーの持久系トップアスリートの成績が伸びたことで脚光を浴びたトレーニング理論です。
これでノルウェーのアスリート、主にクロスカントリーの選手の能力が向上したと言われています。
トライアスロンでは同国のクリスティアン・ブルンメンフェルト選手が Polarized Training に取り組んで東京オリンピックを優勝したことで有名です。
Polarized Training も、低強度の練習に長時間を割き、高強度を短時間としていますが、その間の中強度(高強度と低強度の中間) のトレーニングをしません。
一方 80/20 では、中強度をするのは OK。
中強度は 20% に含めます。(後でも触れます)
他にも違いはあるのですが、ともあれ似て非なるもの、と理解しておいてください。
練習量が少ない人は高強度の比率を上げても良い
GTNの動画の質問コーナーで、下記のような質問が送られてきました。
例えば、その週に1時間の高強度トレーニングを行ったとして、
ウォームアップ 10分
メイン 40分 高速3分+低速1分 のインターバル10本
クールダウン 10分
で構成すると、心拍がゾーン4に達するのは 3分 ×10本の30分間だけです。
この場合、60分間を 80/20 の 20% にカウントすべきですか?
それとも実際に高強度だった 30分間のみを 20% にカウントすべきですか?
これに対する GTN のコーチの回答をまとめると下記のとおりでした。
80/20トレーニングモデルは、ワークアウトを1分単位で細かく分けて計算するようなものではありません。
もっと重要なのは、「80/20モデルがあなたにとって本当に適しているかどうか」という点です。
80/20 モデルは、高ボリュームのトレーニングを行っているハイレベルのアスリート達を対象としています。
彼らが 80/20 モデルを採用する理由は、そのボリュームをこなす中で高強度をやり過ぎないようにするためなんです。
じゃあ練習量が少ない人はどうすれば良いのか? という疑問については、高強度を 20%よりも多くしても良い、と述べてます。
週に 5 時間のトレーニングをしているのであれば、そのほとんどを高強度で行うことができると思います。
突然 80/20 から 0/100 に切り替えろと言っているわけではありません。
先述の Polarized Training 提唱者の Stephen Seiler 博士も Podcast で同様の発言をしています。

1:37:30~
週3回のトレーニングの場合、Polarized Training を適用する必要がありますか?
リカバリータイムが十分あるからおそらく必要ない、もっとハードな練習ができるでしょう。
少し脇に逸れますが、これに続けて、強度を上げることだけを考えずに、1回の練習時間を伸ばすことも重要だよ、と述べております。
そのうち1日の練習時間を長くしてみたらどうだろう。強度だけを考えずに。
(中略)
練習時間を伸ばすことを過小評価してはいけません。
最初の1時間で起きなかったことが 2時間目には起きる。
しかしそこへ到達するには最初の1時間の練習をこなさなければなりません。
高強度の割合は回復力から決める
以下はもう 1つの GTNの動画の質問コーナーの内容です。
80/20トレーニングプランに従って週3回走っています。
テンポランは 80と20のどちらに含まれるのでしょうか?
テンポランは毎週やらないといけないような気がしますが、そうするとスピードトレーニングをする余裕がなくなりますよね。
これに対する GTNコーチの回答はこちら。
テンポはここで言う normal の範疇であり、つまりは中強度は 20% に含める、と述べてます。
80/20 の原則とは、セッションの 80% は easyに、20% だけを normal にします。
これがまさにあなたがおっしゃっているところです。
そしてほとんどのアスリートにとって、低強度/高強度の割合は自身の回復力をベースに考えるべきだ、と述べてます。
もしハードなトレーニングをして、それに回復するのに48時間や72時間かかるとしたら、次のハードセッションはその回復時間に合わせて行う必要があります。
そしてその間は、すべてのトレーニングをイージーまたはとてもイージーにするべきです。
回復に4日かかるなら、ハードなセッションは4日に1回しかできません。
もはや「80/20」は関係なく、「どれだけ回復に時間がかかるか」に基づいて判断すべきなのです。
80/20メソッドから学べる原則はいくつかあり、それはエリートアスリートたちがより良くトレーニングし、パフォーマンスを上げる助けになっていますが、「80/20」という比率に厳密にこだわるのは、ほとんどのアスリートにはフィットしません。
自身の能力に合わせた練習をしよう
私は左手首の骨折・手術を機に、練習量が激減してしまい、心肺も筋力もかなり弱くなってしまいました。
その骨折からある程度回復して練習再開したのですが、つい骨折前の体力を基準にしてしまい、練習の強度・量が現在のフィットネスレベルを超え、関節や筋肉を痛める、そして練習の質と量を下げざるを得なくなる、というのを繰り返しております。
きちんと自分の能力に合わせた練習をしないと、速くなるどころか怪我を繰り返してどんどん遅くなってしまう、というのを身に沁みてます…。
もちろんトレーニング理論を学ぶのは非常に重要です。
ただ、それに振り回されるのではなく、どう自分に落とし込むか、が更に重要だと考えています。
最後に、私も使っているセルフケアのグッズのご紹介。

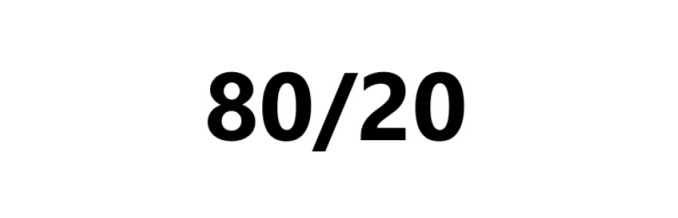







コメント